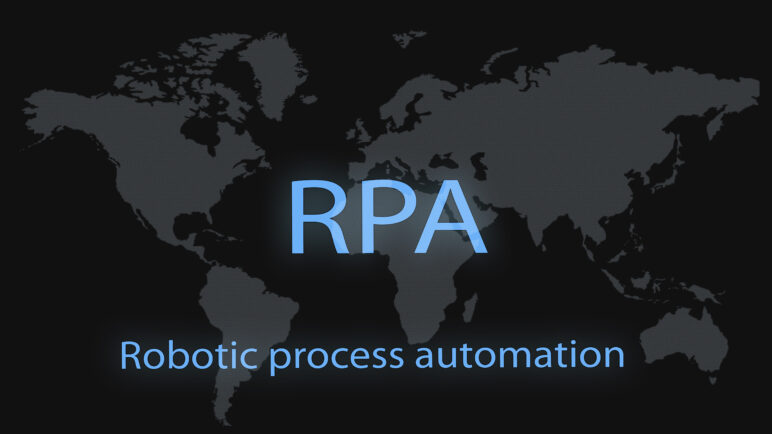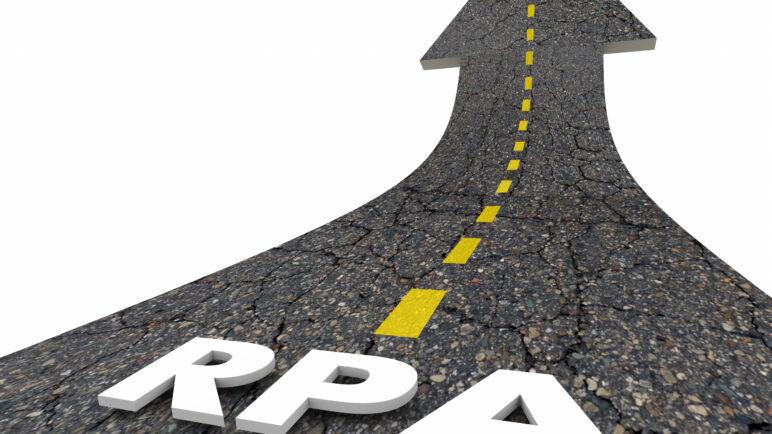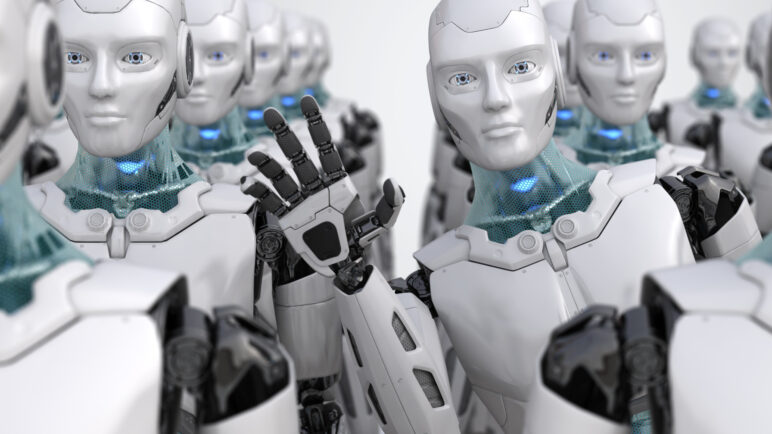RPAコラムRPA-COLUMN
【100%の自動化は必要ない?】自動化可否の判断について
投稿日:2024-01-10

こんにちは。社労業務RPA研究会事務局です。
今回は弊社でおこなっている自動化可否の判断ついてご紹介いたします。
最初に知りたい【どの業務が自動化できるのか】
お問い合わせいただく多くの企業様がRPA導入の際に1番気になるポイントは、「自社内でどの業務がRPAで自動化できるのか」(導入効果)そしてそれに対してかかってくるコストになります。
はじめてのRPA導入の場合、RPAでPC業務を自動化すると聞いても、どの業務がどういう風に自動化されてどれくらい効果が出るのかなど、なかなかピンと来ないのではないでしょうか?
そこで弊社ではZOOMを使った無料カウンセリングにて業務の自動化可否の判断を事前に行い、RPA導入後の自動化イメージをもっていただくところからスタートしております。
自動化可否の判断
弊社エンジニア(社労士事務所での業務をRPA化した実績が多い者が担当します)が業務フローを拝見し自動化可否の判断を行いますが、実は自動化可否の判断は可能か不可能の2つだけではありません。
「自動化可能」「自動化不可能」の2つ以外に「部分的に可能」「フローを変更すれば可能」というパターンがあります。
後者の判断だった場合、現在の業務フローに自動化できない箇所があったとしても業務によっては十分にRPA導入のメリットがあります。
そして実際にRPAを導入している企業様でも「部分的に可能」「フローを変更すれば可能」のパターンでの導入例が非常に多くなっています。
①「部分的に可能」の場合
「現状の業務フロー全てを自動化はできないが、部分的には自動化が可能」という判断。
≪自動化するかどうかのポイント≫
・自動化可能な部分の割合(全体の業務フローの9割なのか1割なのか)
→割合が大きいほど手での作業が減るので自動化の効果は大きい。
・業務の1回あたりの量(労力)と発生頻度
→多ければ自動化可能部分の割合が小さくでも自動化効果を出すことが可能。
・自動化に必要なコスト
→簡単に自動化が可能(シナリオ作成時間が短い、事前準備が必要ないなど)であれば自動化をする価値あり。
②「フローを変更すれば可能」の場合
「現状の業務フローのままでは自動化できないが、フローを変更すれば可能」という判断
≪自動化するかどうかのポイント≫
・フローの変更が可能かどうか
・フロー変更にかかるコストや手間がどれくらいなのか
・自動化した際の効果の大きさ
すぐに自動化を諦めるのはもったいない
企業のご担当者様とお話をさせていただくなかで、RPAでは「システムによってはログインができない」「PDFの文字を読み取れない」などの理由でその業務の自動化自体を断念しようとされるケースはとても多いです。
RPAで自動化できない部分が見つかったとしても、「他のやり方で自動化できないか」「可能な部分だけを自動化した場合の効果」を考えることがRPA導入の成功には重要です。
まとめ
今回は弊社でおこなっている自動化可否の判断ついてご紹介させていただきました。
弊社では導入前に無料カウンセリングを実施し、どの業務がどういう形で自動化できるのかの判断や、自動化フローのご提案もさせて頂きます。
EzRobotは社労士事務所向けに、非常に導入ハードルの低い製品となっております。
- 初期費用0円(導入費用・追加費用・解約費用等一切無し)
- 契約は月毎更新(年間契約等の縛り無し)
- 社労士様特価あり(詳しくはお問い合わせください)
- 無償フルサポート(web会議やチャット、電話等の全てのサポートが追加料金無し)
- 簡単な操作性(PCスキルが低くても、操作が可能です)
- 無料トライアル(無料期間中に自動化を実現させ、効果を体感可能です)
- 専任RPAエンジニアがサポート対応(社労士業務の自動化経験が豊富です)
少しでも興味を持って頂けましたらお気軽にお問い合わせください。
一般企業の業務自動化にも対応しています
中小企業RPA研究会と同様のご案内が可能です。
業務の自動化に興味はあるものの、
「どのように進めていけば良いのかわからない」という場合でもご安心ください。
お気軽にお問い合わせいただければ、最適な進め方や導入のポイントをご説明いたします。