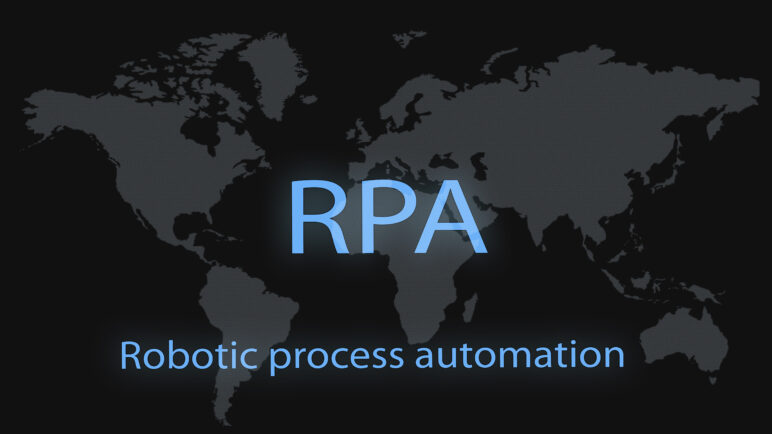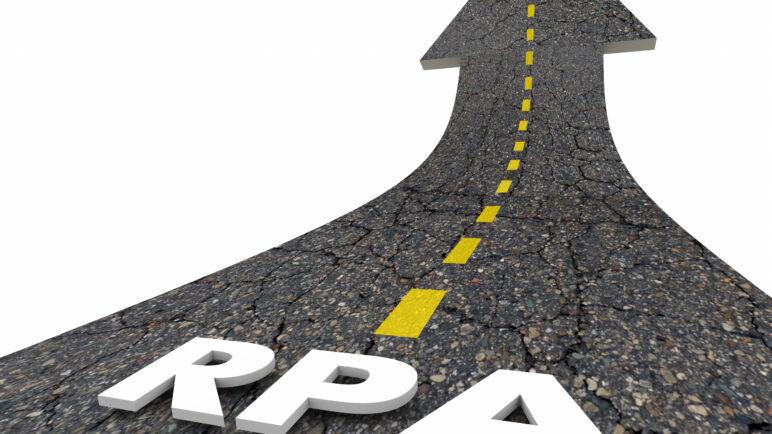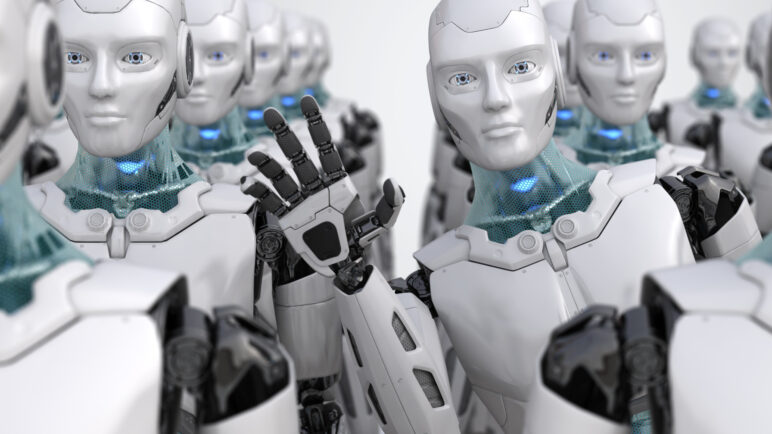RPAコラムRPA-COLUMN
社労士事務所のRPA活用とこれからの未来──AI時代に選ばれる事務所の条件とは?
投稿日:2025-09-25

こんにちは。社労業務RPA研究会事務局です。
今回のコラムでは、
「社労士事務所のRPA活用と今後の未来」をテーマに、
AI技術の進展、デジタル化の加速、顧問先との関係性の変化といった複数の視点から、
これからの社労士業務がどのように進化していくのかを解説します。
“検索力”から“活用力”へ
テクノロジーとの向き合い方が大きく変わる時代
少し前までは、
「分からないことはGoogleで調べる=ググる力」
が、テクノロジー活用の基本とされてきました。
しかし今は状況が一変しています。
-
AIOCR
-
ChatGPTを代表とする対話型AI
-
画像・音声認識AI
-
自動化技術との連携
これらの精度が飛躍的に向上したことで、
“情報を探す力”よりも “問いを立てる力” “活用する力” が求められる時代へと移行しています。
RPAも同様で、
従来の「操作の自動化」から、AIと組み合わせた ハイブリッド運用 が注目されています。
こうしたツールを使いこなすスキルは、
社労士だけではなく、すべての業界に求められつつあります。
中でも EzRobotのようなノーコードRPA は、
デジタル活用の“第一歩”として最適です。
「顧問先がアナログだから進まない」は過去の話
デジタル化の壁は、社労士の支援によって超えられる
現場でよく聞かれる悩みのひとつが、
-
「顧問先がアナログすぎる」
-
「紙で郵送してほしいと言われる」
-
「FAX文化が残っていて業務改善が進まない」
といった声です。
たしかに、RPAを導入しても顧問先がアナログのままでは、
結局“手作業部分”が残り、効果が感じられないケースもあります。
しかし、だからこそ社労士の存在価値が高まっています。
顧問先の業務改善に最も近い位置で伴走できるのは社労士だけ。
手続き代行の枠を超えて、
“業務そのもの”をデジタル化へ導くことが、これからの時代に求められる役割です。
未来を切り開くポイントは「部分最適」で終わらせないこと
小さく始めて、大きく育てるRPA運用
自動化を始める際に重要なのは、
“最初から全部自動化しようとしない”ことです。
まずは、次のような 時間がかかりやすい業務 から着手するのがおすすめです。
-
公文書取得
-
勤怠データの加工・入力
-
請求書作成・送付
-
手続き書類のアップロード
-
各種データ移行作業
事務所内の効率化から始め、
慣れてきたら顧問先との共有業務へと広げていくことで、
“便利さ”が双方にとって実感できる形になります。
EzRobotは動作が柔軟で、
小規模な自動化から大規模なワークフロー構築まで対応可能。
「思っていた以上に業務が楽になった」という声が多い理由はここにあります。
まとめ
EzRobotは“省力化ツール”ではなく“未来を拓く選択”
EzRobotの導入は、
単純な“効率化”のためだけではありません。
それは、
「社労士の働き方」を再設計する選択肢 と言えます。
-
業務効率化で生まれた時間を相談・提案に充てられる
-
顧問先との関係性がより濃くなる
-
属人化が解消され、事務所の安定運営につながる
-
顧問先のデジタル化にも伴走できる
-
AI活用のスキルが自然と身に付く
今後は、
RPAだけでなくAIを活用し、顧問先全体の最適化まで提案できる社労士 が求められます。
EzRobotをご導入いただいた場合は、
RPA運用に限らず、最新のAIツールの活用方法まで、
研究会として全力でサポートいたします。
EzRobotは社労士事務所向けに、非常に導入ハードルの低い製品となっております。
- 初期費用0円(導入費用・追加費用・解約費用等一切無し)
- 契約は月毎更新(年間契約等の縛り無し)
- 社労士様特価あり(詳しくはお問い合わせください)
- 無償フルサポート(web会議やチャット、電話等の全てのサポートが追加料金無し)
- 簡単な操作性(PCスキルが低くても、操作が可能です)
- 無料トライアル(無料期間中に自動化を実現させ、効果を体感可能です)
- 専任RPAエンジニアがサポート対応(社労士業務の自動化経験が豊富です)
少しでも興味を持って頂けましたらお気軽にお問い合わせください。
一般企業の業務自動化にも対応しています
中小企業RPA研究会と同様のご案内が可能です。
業務の自動化に興味はあるものの、
「どのように進めていけば良いのかわからない」という場合でもご安心ください。
お気軽にお問い合わせいただければ、最適な進め方や導入のポイントをご説明いたします。